
事実を毎日メモしたら、50文字の視界が7万文字の世界になってた話
みなさん、メモってどれくらい書いてますか?
日常でも、仕事でも、なんでもいいんですけど。あっ、でも、できればタスク以外がいいです。発見したこと、考えたこと、感じたことなら、すごくいい。
「なんに使うかわからないけど、覚えておきたいメモ」だったら、もう、最高です。それはわたしが一番好きなやつです。
毎日、なにかしら書いてるよっていう人、いたら手をあげてください。
おっ、あなたはすばらしい。わたしも書いてるので、わたしもすばらしい。
なぜかというと、もうめったにやらないことを決めたのですが、今年の前半はいわゆる文章講座のようなものをいくつか引き受けていて、そこで一番たくさんもらった質問は「どうすれば、おもしろいエッセイを書けますか」でした。
そんなもん、わたしが知りたいのですが、昔から“事実は小説より奇なり”という言葉があるのは確かです。つまり、奇特な事実を見つけたらいい。
「なんでもいいから、いいなと思った事実をメモするのはどうでしょう」
わたしは答えました。
同時にわたしは、それを自分でやってみることにしました。
ちなみに、文章講座で200人くらいの人に伝えましたが、1週間たって「毎日メモできた人?」って聞くと、5人もいませんでした。
だから、すごいんです。
藪から棒に、すみません。
作家になった、岸田奈美と申します。
一年間のメモが、わたしを変えてくれた話をします
一年前のわたしは、悩んでいました。
このままずっと楽しい文章を書いて、楽しく生きてみたいけど、どうやら書けることは半年も経たずになくなりそうだったからです。
そのころわたしは、「家族の話と奇跡の話の二本槍兵士」でした。
文章にしたらおもしろいくらいの家族との思い出話なんて、この身体には両手で数えるほどしか持っていません。
奇跡が起こりやすい星のもとに生まれたけど、そんなの、二ヶ月に一回あればいい方です。
つまり、書くことがなくなる。ずっとこのまま叱られながら会社員をやらないといけない。
ぼくはいやだ!
そんなわけで、エッセイのネタになればと、メモをとりはじめることにしました。
だいたいのルールは、こんな感じです。
道具:
iPhoneにデフォルトで入っているメモ(機種変でも自動で引き継がれるのでかしこい)
書くこと:
おもしろいなと思ったことはなんでも、他人の言葉や映画の台詞でもいい
文字数:
1日、50文字以上を毎日続ける
わたしの場合は、これで書く仕事を続けられるかが決まるので、必死です。基本的に学校の宿題など提出できた方が少なかったですが、これはがんばりました。
はじめたばかりの、わたしのメモです。

これを、どないせえと言うねん。
おもしろいというか、失礼なことを書いてしまっています。
パパイヤ鈴木さんと葉加瀬太郎さんは、ここを読むことはきっとないでしょう。ただ、茂木健一郎さんはお話したことないけど、Twitterにはいらっしゃるからな……もし怒られたら、謝ります。いまは茂木さんだけ、見分けがつくようになったので。
まあ、最初はたぶん、こんなもんです。
ちなみに、浅すぎるこれらがエッセイになることはありませんでした。この時はまだ、家族の思い出話や奇跡話を少しずつ書いて、しのいでいました。
でも、ちょっとしたラジオ出演などで、アドリブで話す材料にはなってよかったなと思います。
一ヶ月続けてみたら、だいたい2000文字になっていました。
みなさんのなかに、こんな経験がある人はいませんか。
「Instagramをはじめたら、きれいな景色や料理を撮る回数が増えた」
イイネ!って言われるとうれしいから、目にも美しいものを探そうとする。頭より先に、心が動いて、パシャるのがクセになる。
メモを書くようになると、これと同じことが起こりました。
人が作ったものや、人が話すことが、だんだんとおもしろくなってきたんです。
このときの状態を、わたしは、とっかかりが増えたと言っています。フッとした時に「なんか、今の、いいな」って、とっかかるんです。
メモを書くために、目と耳の解像度を、無意識に上げました。
書く。
とっかかることが、増える。
また、書く。
この繰り返しで、1年が経った、いま。
iphoneのメモの文字数は、7万文字になっていました。
1日50文字だったのが、今月は平均すると600文字。一ヶ月に2万文字近く、書きためたことになります。
一年前のわたしとは、見ているもの、聞こえていることが、10倍も違うのです。パカパカ携帯のカメラから、ライカのカメラになったような。

こういう、長めのメモが多くなりました。パヤパヤ。失礼なことも、たぶん、ないぞ。イエーイ。
もうこれだけで、短いエッセイくらいにはなりそうですね。
メモを取り続けて、ダメな自分にハッとしたこと
最近はもっぱら、自分がうんうん唸って悩み、ようやくピーン!と気づいて編み出した、新しい考えを人に話すと「それ同じようなことを糸井重里さんが10年前に言ってたよ」と誰かから言われてしまう呪いにかかっています。嬉しいが、本音はとても悔しい。
その糸井さんに会ったとき、言われたことです。
「岸田さん。最近、トラブルがなかった日は『あ〜あ、ネタがないや』って、ガッカリしてないかい?」
してます。
トラブルは、おもしろいエッセイになるので。
「それはね、おすすめしないな。だって日常で不幸を探すのがクセになる。不幸になっちゃうよ」
はっ。
これはもう、びっくりでした。わたしはネタを探すあまり、自分が不幸でかわいそうになる瞬間を、心のどこかで期待していたんです。
幸せになりたくて、書いていたはずなのに。アカン。
なので、いまは意識的に「嬉しかったこと」「愛しかったこと」を探すようにしています。どんな不条理にも、どんな空虚にも、探すためにカッと目を見開けば、美しく、愛しいところが見つかることに気づきました。
愛を見て、愛を語る言葉が、わたしのなかに増えました。
編集者の佐渡島さんからはいつも「自分の感情を細かく観察しよう。一流の作家は、感情を書くだけですごい作品になる」と教えてもらっています。
佐渡島さんとは毎週、定例で雑談をしているので、その時に話すため、メモの内容に「その事実に、わたしは寂しいとか嬉しいとか、どんな感情を持ったのか?」も付け足すようにしました。
「世界は贈与でできている」の著者・近内悠太さんから、気づかせてもらったこともありました。
それは「ぼくたちは、“あったかもしれない可能性”に気づき、幸せになるために、物語を書いている」という言葉。
つまり、事実をそれだけで終わらせず、想像力をもって書き足していくこともやってみました。
最終的にわたしは、わたしに問いかけるメモを書いている
愛しいところを、見ようとする。
自分の感情をていねいに観察する。
あったかもしれない可能性を想像する。
メモにただ事実を書くことに慣れたわたしは、先輩たちから教えてもらった、この3つをやってみることにしました。
コツは「どんなところが愛しい?」「なんで怒ったの?」「これってどんな背景があったらおもしろい?」と、じぶんに質問してみることです。
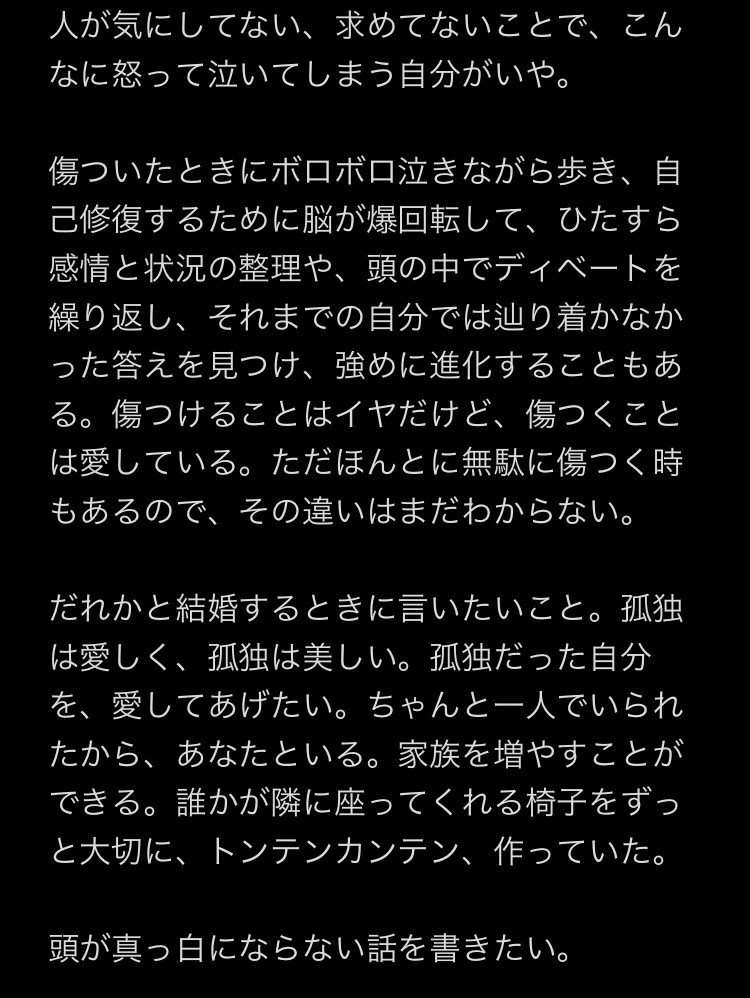
ずいぶん暗いですが、これがわたしの最新日付のメモです。
こんなにたくさん書いていますが、起こったことは、たったひとつだけ。
「いろんな人が集まる会で、傷つくことを言われて、言い返せなかった自分がイヤだった」
これでした。
一年前のわたしなら、ただ、涙をのんで「ちくしょう!」と吐き捨てながら、一風堂あたりでラーメンをしけこみ、オールナイトニッポンを聴いていたことでしょう。
でも、いまのわたしには、メモがあります。
書くために。
ただ、書くために、わたしは、事実の見方を変えました。たった50文字の視界が、7万文字の世界になりました。
これから先、どんなにしんどいことがあっても、きっと7万文字、いや、数十万文字になっている世界は、わたしに前を向かせてくれます。
メモをとることが、わたしという味方を作ってくれたのです。
あなたも、いっちょかみ、どうですか。
ここからは、最近書いたメモを、ちょっと細かく紹介してみます。2021年の大きなテーマになることばかりです。
渋谷のスクランブル交差点とおじさんのアカシア(マガジン読者限定)
渋谷のスクランブル交差点にいた、汚れた服で段ボールにくるまってた人、BUMP OF CHICKENの新曲を口ずさんでいた。いいなあ。同じ曲を気に入ってたことが嬉しい。
たしか曲は、BUMP OF CHIKENの「アカシア」でした。発表されたばかりの曲で、わたしもまだ歌詞を覚えていませんでした。
それが渋谷のスクランブル交差点の大きなビジョンで流れたとき。
ふっと横を見ると、汚れた服で、段ボールにくるまり、空きカンがたくさん入った袋を足元に置いて、植垣のコンクリートに横になっていたおじさんが。
「透明よりもきれいな あの輝きを確かめにいこう ♪」
うそやろ、と声の源を二度見してしまいました。おじさんでした。
これはとても失礼な憶測ですが、おじさんはどう見ても、BUMPの新譜を買うようにも、発表されたばかりのPVをYoutubeで再生するようには思えなかった。
だからわたしは、おどろきました。
青色になった信号で、交差点を渡りながら、わたしは嬉しくなりました。
「びっくりしたけど、おじさんもBUMPが好きなんだなあ。いい歌だもんなあ」
ここまでは、ただの事実です。おじさんが、BUMPを口ずさんでいた、それだけ。
このメモに“あったかもしれない可能性”をつけたしたのは、数日後のこと。
ドキュメンタリー映像を作っているディレクターさんと、お話をする機会がありました。
そのディレクターさんが言うには、人気のバラエティ番組を作れば1億円が手に入るが、ドキュメンタリー番組は500万円が入ればいいほう、だそうです。
「それでもぼくは、ドキュメンタリーだけ作り続けてるんです」
「儲からないし、密着取材は大変なのに、どうしてですか?」
「昔、左官さんの取材をしたことがあって、その時の感情が忘れられないんです。左官さんが、壁に5mほどの線を鉛筆で引いたときでした。定規も使わず、ピシーッと、まっすぐ。それってすごくないですか」
「すごいですね」
「でも、左官さんは何事もなかったように終えて、まわりの職人さんもいちいち褒めたりしなくて。現場では当たり前なんですよ。つまり、僕がこれに気づいて、ぼくが撮らないと、日本中の人たちはこの技術と美しさに気づくこともない。それがドキュメンタリーのやりがいで、ぼくの使命です」
彼の使命は、だれも気づいていない美しさや努力を見つけて、それを映像にして、日本中に伝えること。そして、守り、次代に継いでいくこと。
ものすごく大切な使命に思えました。わたしも、そういうエッセイを書きたいと思いました。
そのとき、ハッと思い出したのが、あのおじさんのことです。
「そうか。おじさんはBUMPが好きだったわけじゃなくて、毎日毎日、ずっとあの場所にいるから、ビジョンから流れてくるBUMPの歌を覚えたんだ」
どうしてそんなことに気づかなかったのか、と思いました。
同時に、嬉しかった気持ちが、もっともっとふくらみました。
だって、ぜんぜん好きじゃないアーティストなのに、聞こえてきたフレーズをおじさんが所構わず口ずさみたくなるくらい、「アカシア」は素晴らしい歌だったのだから。
もちろんそれは、勝手な可能性のひとつにしかすぎません。だけど、BUMPが好きなわたしにとっては、真実が判明するまではそう捉えていた方が、幸せなのです。
自分を幸せにするために、いくつもの事実から、いちばんいい物語を導き出す。そういうことをやっていきたいと思っています。
多様性を認める仕事は、孤独をつくる仕事だった(マガジン読者限定)
わたしは前職で9年間、ミライロという会社で働いていました。障害のある人が生きやすくなるように、ユニバーサルデザインやダイバーシティ(多様性)をすすめる会社です。
わたしは会社員に向いていないことが最終的にわかったけど、すごくやりがいのある仕事でした。
なんのために、あんなにもがんばれたかというと、たぶん「孤独をなくすため」です。
わたしは孤独でした。父が亡くなり、弟と母には障害があった。できていたことが、できなくなった。
神戸の田舎という小さな社会で、まったく同じ苦しみを抱えている人は、ミライロに入社するまで、まわりにはいませんでした。なにを言われても「どうせわからない」と、孤独になっていました。そんな状態がイヤだったので、がむしゃらに働きました。
ユニバーサルデザインな建物の設計を手伝ったり、ダイバーシティな採用を進める研修をしたり、いろんなことをやってきました。
それでよくなったこともたくさんあったのですが、最終的にわたしは、心のどこかで「それでもわたし自身のことは、社員にはわかってもらえなかった」と、がっかりしていました。
それで、作家になりました。
でも、こうやってエッセイを書いて、人に会って、感情を見つめていくたびに思うんです。やっぱり、わたしの痛みは、わたしにしかわからないと。
わかりやすい言葉にすれば、人にも伝わります。
だけど、それは、わかりやすくした時点で、100%おなじ痛みを再現できているわけではありません。喜びにしたって、そうです。
つまり、結局のところ、人は孤独なんですね。
寂しくないように、取り残さないようにすることは、できる。でもそれは孤独を前提として、お互いの孤独を尊重し、愛し、寄り添うことなんです。
9年間、わたしは「孤独なんてない。みんなで違いを受け入れよう」ということを言っていたので、それがどんなに無謀なことだったかを思い知りました。
性別は、男と女、だけで区別されていた時代がありました。
もちろんそれはよくないことですが、区別だけで見れば「男チームと女チームの2種類しかないので、孤独ではない」とも言えたかもしれません。
だけど、人々が声をあげ、LGBTQという言葉も広まり、性別は2種類ではなくなりました。
さらにそこへ、国籍の違い、年齢の違い、文化の違い、障害の有無など「新しい区別」が入ってくると、もはや「誰ひとりとして同じ人はいない」社会になってきました。
違いを認め、違いを尊重するということは、「人はもともと、みんな孤独」を思い出させることだったのだ、と思いました。
だからこれからは、むやみに「孤独にしない」「孤独じゃないのが正しい」といって、悩みも痛みも喜びも100%シンクロできるわけじゃないのに、一緒くたに混ぜることを強制してはダメなんでしょう。
人はみんな孤独なんだから、孤独を愛して、孤独を尊重して、「あなたもわたしも孤独だけど、気が合うときは一緒にいようね」と、くっついたり離れたりできるのが、いいと思うんです。
思えばわたしは、それをずっとやってきていました。
7歳のときに、父にiMacを買ってもらってから。わたしの友人は、話のあわない小学校の子でも、いじめてくる高校生の子でもありません。
一度も会ったことのない、顔も年齢もわからない、画面の向こうでチャットをしているあなただったんです。
当時は「そんなの本当の友だちじゃない」って、先生は認めてくれなかった。でも今は違う。ZOOMでしゃべっただけなのに友だち、一度も出社して会ってないのに同僚、っていう関係性ができはじめている時代。
一人でいる自分が好きだから、みんなといる自分も好きになれる。
わたしはそういうものだと思うんです。だから、来年は、一人という孤独をどれだけ愛して、その上でみんなとつながれるか、考えていこうと思います。
いいなと思ったら応援しよう!


