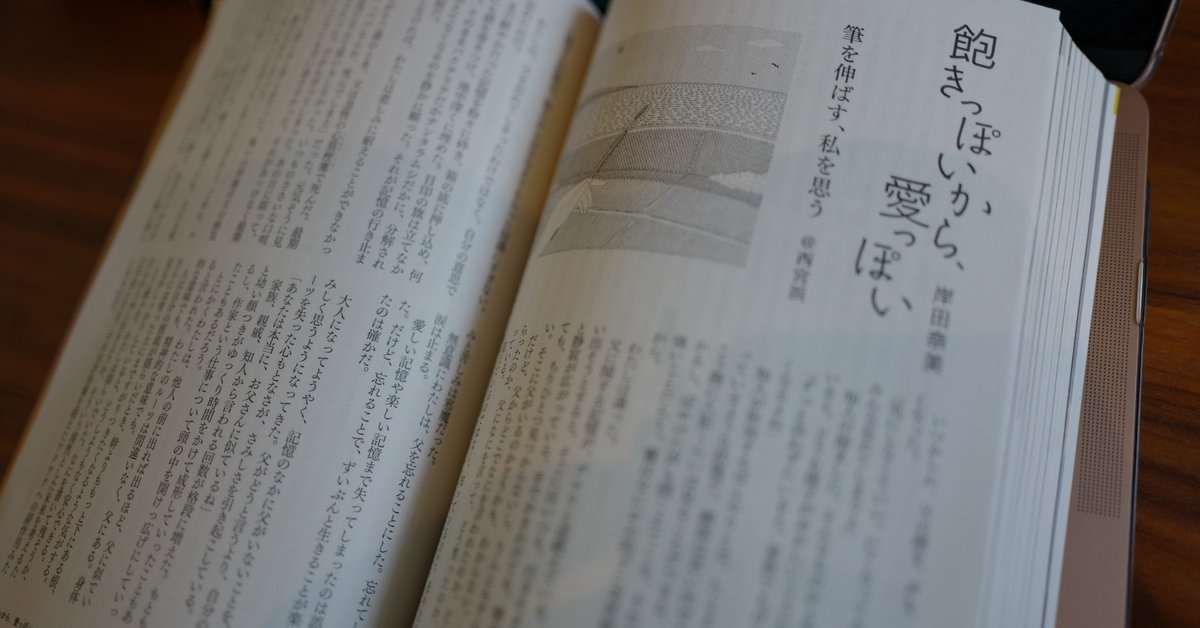
飽きっぽいから、愛っぽい|筆を伸ばす、私を思う @西宮浜
講談社「小説現代」2020年9月号(8月21日発売)から、新連載を始めさせてもらうことになりました。

もともと、生い立ちに関する連載をしていたのですが、わたしが講談社の徳を積みまくる系敏腕編集・山下さんに甘えまくって、好き勝手に書きすぎたところ、当初の連載予定よりも早く現実に時間軸が追いついてしまうという、爆裂的な計画性のなさをふんだんに露呈する事態となってしまい。
「過去」と「場所」にまつわる連載「飽きっぽいから、愛っぽい」を、新しく書いていきます。
キナリ☆マガジン購読者限定で、「小説現代9月号」に掲載している本文をnoteでも公開します。(講談社さんありがとうございます)

かわいすぎる表紙イラストは、中村隆さんの書き下ろしです。
筆を伸ばす、私を思う@西宮
いつからか、父の顔を、声を、言葉を、さっぱり思い出せなくなった。
「気にしなくていい。亡くなってから十五年も経っていたら、みんな忘れてしまうよ」
知人の励ましに、そんなものかと安心しながら会話を続けていると、どうも様子がおかしいことに気づいた。
「ずっと会わずにいると、家族でもぼんやりとしか思い出せなくなるよね」
知人が形容するぼんやりとは、たとえるなら記憶に霧がかかっているような状態だ。細部は思い出せなくても、水蒸気の向こう側に人影くらいは見ることができる。だいたいの背丈もわかるし、ぼやけた声も聴こえてくる。
それだけで、どんなに心強いことだろう。霧はなにかの拍子に突然晴れたりもするのだから。
わたしは違った。
父に関する記憶が、ブツリと途絶えている。
頭の中で父を思い出そうとすると、そこにはいつも、行き止まりみたいな暗闇と静寂が広がっている。手でかきわけても、懐中電灯で照らしても、ちりひとつ見つからないし、うんともすんとも聴こえない。
そこに父がいるのかどうかも、わからない。
だけど、父からどこでなにを言われたのか、どんなものをもらったのか、なにを言って、どう笑ったのか、わたしは知っている。
覚えているのではなく、知っているのだ。母や父の友人から、懐かしそうに語ってもらったことによって。つまりわたしの父に関する記憶は、他人から分け与えてもらった知識にすぎない。
わたしは、父を忘れてしまったわけではなく、自分の意思で忘れたのだ。
まだ鮮やかだった記憶を粉々に砕き、箱の底に押し込め、何重にも鎖を巻きつけ、地中深くに埋めた。目印の旗は立てなかった。そのままバクテリアだかナンタラムシだかに、分解されて、消えてなくなるのを静かに願った。それが記憶の行き止まりの真相だ。
そうしなければ、わたしは悲しみに耐えることができなかった。
わたしが十三歳のとき、父は急性の心筋梗塞で死んだ。最期の会話は「パパなんか、死んでしまえ」だった。
元気そうに見えた。病気だなんて思いもしなかった。いつものささいな口喧嘩のつもりだった。だから言ってしまった。あの日に限って、父はわたしになにも言い返さなかった。それがあっけなく最期になった。
耐えられない悲しみと苦しみだった。呪いの対象は父の病気ではなく、愚かなわたしだった。
「どうしてあんなことを言ってしまったんだろう。ごめん、パパ、ごめんなさい」
遺灰の前で考えても考えても、謝っても謝っても、なにも変わらなかった。すべてが手遅れだった。
それでもわたしは、残された家族と一緒に、生きていかなければいけない。日々を歩いていくためには、ズシリと重い悲しみと苦しみは邪魔だった。
無意識にわたしは、父を忘れることにした。忘れてしまえば、涙は止まる。
愛しい記憶や楽しい記憶まで失ってしまったのは誤算だった。だけど、忘れることで、ずいぶんと生きることが楽になったのは確かだ。
大人になってようやく、記憶のなかに父がいないことを、さみしく思うようになってきた。父がどうと言うより、自分のルーツを失った心もとなさが、さみしさを引き起こしている。
「あなたは本当に、お父さんに似ているね」
家族、親戚、知人から言われる回数が格段に増えた。もともと幼い顔つきがゆっくり時間をかけて成形していったこともあるし、作家という仕事について頭の中を開けっ広げにしていったこともあるだろう。
とにかくわたしは、他人の前に出れば出るほど、父に似ていると言われた。わたしのルーツは間違いなく、父にある。身体的な意味でも、精神的な意味でも。
人は自分の根底が揺らいだとき、幹よりももっと下にある根、さらには育った土にまですがりつきたくなるような気がする。足元がしっかりしていると、どうしようもなく安心できる。
ここ数ヶ月、わたしは揺らいでいた。なにを書いて残そうか、なんのために生きようか、そういう漠然とした未来を考えるたび不安になる。それは許容量を越えたワクワクへの副作用みたいなものだ。
「父だったら、なんて言っただろうか」
わたしにとって父とは、途方もない憧れの存在だった。常に好奇心と義憤にかられ、未知に挑戦し、ユーモアと愛をも忘れない父だった。頼もしいルーツに、わたしはすがりたくなった。
だけど、だめだった。何度思い返そうとしても、すがるほどの実体を持った父は、記憶のどこにも見当たらない。
7歳のときにiMacと輸入版のファービーを買ってくれたこと、風呂の追い焚きをする度に足が溶けたフリをすること、十三歳のハローワークをわたしによこして読ませたこと。断片的な笑い話は思い浮かぶけれど、それはすべて、母から説明された知識だった。知識はただそこにあるだけで、揺らぐわたしに語りかけてはくれない。
記憶を埋めた土を無理やり掘り起こそうとしてみると、火花がみたいに、パラパラと小さな記憶が飛び散ることがある。それは、父と訪れた場所へ足を踏み入れたとき、急に出会った。
先日、母の思いつきで、兵庫県西宮市を訪れた。
訪れたと言っても、実家のある神戸から大阪まで車で向かうついでに、ちょっと寄ってみただけだ。
西宮は父の故郷であり、父と母が結婚して最初にアパートを借り、父が起業してからはオフィスを構えた街だった。父の実家、アパート、オフィス、とたっぷり時間をかけながら順番に車でまわっていくと、母は「懐かしい」と嬉しそうにつぶやいた。
わたしは相変わらず、ちっとも思い出せなかった。でも母があまりに楽しそうだったので「そうやね」と相づちを打っていた。
海が好きだという母が、追憶ツアーのゴールとして西宮浜へとハンドルを切ったとき、わたしはびっくりした。
パチパチと、記憶の火花が散ったのだ。
「ここに似たところ、パパと来たことある」
それは知識でも妄想でもない、記憶だった。きれいとはお世辞にも言えない海と、鼻につく磯の匂いと、地平線の果てまで続く灰色の堤防。この西宮浜と同じ場所だったかどうかはわからない。だけど、似たような景色を、かつてわたしは父と眺めたことがある。
わたしはまだ、小学校に入ったばかりだった。
堤防の一角で、子どもたちが絵を描いていた。なんでだったか理由はわからないけど、とにかくそういうイベントのようだ。堤防のキャンバスを、縦横無尽に泳ぐように、とんでもない色のサメやクジラやタコが描かれていて。
父はわたしに、どこからか借りてきた絵筆とパレットを渡して。
「好きに描いてええんやで」
そのあとすぐ、父の眉が下がったのを覚えている。困ったような、がっかりしたような。わたしは、好きに描こうとしなかったからだ。
「どうして描かんねん」
「こんなところに描いたことないし」
「べつにええやん、失敗しても」
「ううん、なんかなあ」
なんだかんだ言って、わたしはもじもじと絵筆とパレットを交互に見た。どうして描こうとしなかったのか、なんとなく、いまのわたしなら想像がつく。
わたしは飽きっぽい人間だ。
絵や工作といったものを、最後まで気を抜かず、ていねいに完成させたことの方が少ない。最初の十五分くらい取り組んでみたら、なんだかやる気が起きなくなって、あとは惰性で完成させて、あっさりと興味を失ってしまう。完成品を自宅へ持ち帰らず、学校でゴミみたいに捨ててしまうこともしょっちゅうだった。
大人になっても変わらない。ギター、ドラム、テニス、ピラティス、いろんな習い事を始めてみたものの、ちょっとできるようになると、すぐに放り投げてしまった。わたしの自宅の物置はそういう薄っぺらい好奇心の残骸であふれている。
時には、仕事においても。
飽きっぽさは、時に周囲から悪意ととられ、恥ずべき短所であるという自覚があった。
「社会人なんだから、最後までしっかりやり遂げなよ。有言実行って大切なんだから」
正論だった。だからわたしは、ずっと自分を恥じてきた。ていねいで、まじめで、根気の良い社会人になろうと思った。
でも、硬く結んだはずのその決意すらもあっさりと霧散していった。筋金入りの飽きっぽさだ。最近になって、自分のどうしようもない飽きっぽさへの、捉え方が変わってきた。
「岸田さんは愛にあふれていて、他人にも愛を求める人なんだね」
わたしのエッセイを読んでくれた人が、そんなことを言った。
そうかもしれない。わたしが心の底から気に入るのは、そこに確かな愛のあるものが圧倒的に多い。愛によって作られたもの、長く愛されていること、自分も他人も愛しているひと。芸能人が自分の偏愛っぷりを披露するバラエティ番組なんて、欠かさずチェックするくらい大好きだ。
そう言えば、父の部屋に置かれていたものたちも、そうだった。
スウェーデンの職人が作った、重くて大きな黒い革のリュック。憧れのドイツで買ってきた水彩絵具、木製パズル。美しい葉っぱの形をした、磁力で浮いているペンスタンド。子どものわたしの目には「なんかヘンなもの」と映っていたが、それらは誰かしらの愛にあふれていた。その証拠に、それらはわたしによって回収され、いまでは実家のわたしの部屋に移住している。
わたしは、愛にあふれ、愛せるものしか、手に入れたくない人間なのだ。それはきっと、父から脈々と受け継がれてきた性質。
だから、工作も、趣味も、仕事も、長く続かなかったのかもしれない。「これはわたしが愛せる完成形にはならない」と、途中で気づいてしまったから。
頭の中にはいつだって、「愛せそうなもの」の理想図があった。それは父が、わたしに素敵なものをたくさん見せてくれたからだと思う。でも、いざ頭の中の理想図を取り出そうとすると、透明な壁に阻まれる。壁の正体は、手先の不器用さや、才能の乏しさだったりするのだけど、ともかくその時点で理想を形にすることは難しいだろうと悟る。
愛せないものに、最後まで手間暇をかける理由はない。だから途中で投げ出してしまうのだ。
恥ずべき短所が、少しだけ誇るべき長所のように思えた。
あの日。堤防へ絵筆を押しつけることをだらだらと拒んだのは、堤防みたいに大きなものに、絵を描いたことがなかったからだ。描いたことがないから、失敗は免れない。愛せないとわかっているものを、大好きな父の前で、作って投げ出してしまうのが嫌だった。
「ほら。ここあいてるから、入れてもらい」
そう言って父は、堤防にむらがる子どもたちの間にぽっかりできたスペースへとわたしを押し込んだ。
しぶしぶ、わたしは絵筆を押しつけた。なにを描いたかは忘れてしまった。覚えていないということは、記憶するほど愛せるものではなかったはずだけど。
「ええやん。うまい、うまいわ」
父はたしか、誇らしそうに、笑っていたはずだ。西宮浜へ訪れたわたしの脳裏に蘇ったのは、堤防の絵ではなく、父の笑った顔だった。
あのとき父が褒めたのはきっと、絵ではなくて、迷いながらも一歩を踏み出した、わたしの姿だったのだろう。
父は、たしかにわたしを愛してくれていた。
だからいま、ふとした拍子に思い出したのだ。いくら地中深くに埋めたとしても、消えてなくならない記憶がある。救われた気がした。
いまでもわたしは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへ行くと、どうしてもバック・トゥ・ザ・フューチャーに乗ることができない。父が最後に連れて行ってくれた遊園地であり、アトラクションであるからだ。
父についてほとんどのことを思い出せないし、ドクが発明したデロリアンで過去へと飛ぶこともできない。だからせめて、忘れてしまった父のことを心の底から愛し、歩んでいこうと思う。
父の記憶は確かでなくても、父がわたしを愛してくれたことは確かだから。
「父だったらなんて言っただろうか」ではなく「きっと父ならこう言うだろう」と、言い聞かせていく。行き止まりになった記憶の暗闇に、新たな記憶という映像を投写する。それは作り物かもしれない。
だけど、父が愛したわたしが描いたのならばきっと、父は許してくれるだろう。
「好きに描いてええんやで」
西宮浜の堤防で、声が聞こえた気がした。
いいなと思ったら応援しよう!


